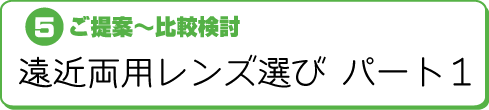 |
遠近両用レンズは度数以外にも比較項目があります。
| ※累進帯長の違い ユレ・歪み・視野の広さに影響します。 |
フレームにあったレンズ選択? レンズにあったフレーム選択?
| ※レンズ種類(累進設計) 外面累進 内面累進 両面累進 |
|
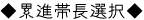 累進帯長の詳しい説明はコチラ 累進帯長の詳しい説明はコチラ |
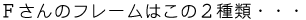 |
|
|
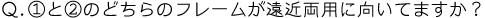 |
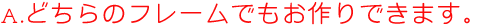 |
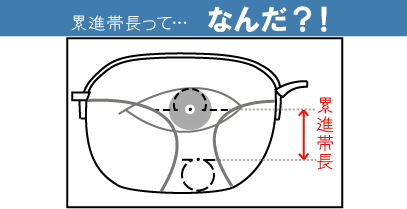 |
【累進帯長】
遠くを見るポイントから近くを見るポイントまでの距離。
見た目には分かりませんが、遠近両用レンズには必ず累進帯が存在し、
この累進帯で度数が変化します。
累進帯長も長いものから短いものまであり、長さによってレンズ性質が変わります。
|
| 累進帯長 |
長さ |
フレームサイズ |
見え方 |
特徴 |
 |
 |

縦幅24mm〜30mm推奨 |
視野 |
近方重視。
小さいフレーム対応。
遠近両用に慣れた方にオススメ。 |
| 狭い |
| ユレ・歪み |
| 多い |
 |
 |

縦幅30mm〜40mm推奨 |
視野 |
中間重視。
スタンダードタイプ。
初めての方にオススメ。 |
| 普通 |
| ユレ・歪み |
| 普通 |
 |
 |

縦幅40mm以上推奨 |
視野 |
遠方重視。
運転やスポーツ・アウトドアなどにオススメ。 |
| 広い |
| ユレ・歪み |
| 少ない |
|

度数設定・加入度・フレーム形状・用途によって選びます。
①と②のフレームでは縦幅が違う為、お勧めする累進帯長も変わってきます。
|
| メガネ屋さんの説明 |
 |
『度数・加入度が同じでもフレーム形状によって累進帯長が変わります』
『累進帯長の違う2タイプのレンズの見え方を体験して下さい。』 |
 |
Fさんの感想 |
『累進帯長が長いタイプの方がが自然に見える!』
『短いタイプは少し揺れるが、それほど気にならない。』 |
| メガネ屋さんの説明 |
 |
『今回は初めての遠近両用なの普通のタイプ(14mm)をオススメします』
『大きい方のメガネを使いませんか?』 |
 |
Fさんの感想 |
『そうですね。初めての遠近なので普通の長さ(14mm)のレンズにします』
|
|
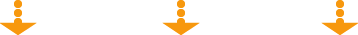 |

|
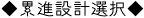 遠近両用レンズ設計も違いがあります。 遠近両用レンズ設計も違いがあります。 |
まだまだ、選ぶことがあります。・・・【商品選び】
遠近両用のグレード? 見え方に違いがあるの? 価格は?
グレードの違い
視野を広げ、ユレ・歪みを防止する性能の差です。
加入が強くなる場合や歪みなどが気になる方は、上級の製品をオススメ致します。 |
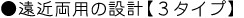 累進設計の詳しい説明はコチラ 累進設計の詳しい説明はコチラ |
| 両面非球面設計 |
両面累進、両面設計・両面複合等と呼ばれ、メーカーの最上級レンズ。
レンズの両面にユレ・歪みを低減する技術が集結。
|
| 内面非球面設計 |
外面累進に比べ、視野が広くなり、
遠近両用の弱点であるユレ・歪みを軽減。
|
| 外面非球面設計 |
一般的な遠近両用累進設計。
10年以上前から開発されています。
|
|
|
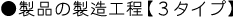 製造工程の詳しい説明はコチラ 製造工程の詳しい説明はコチラ |
オーダーメイド設計
【最適個別製造】 |
一枚一枚のレンズをゼロから作る最適数値での設計を追及
一人一人の個々の条件に合わせて個別数値で度数データを設計製造。 |
セミオーダー設計
【最良化製造】 |
何タイプかの種類の中から個別の条件を考慮。
適正な数値を基にして、度数データを設計製造。 |
ベーシック設計
【既成製造】 |
1種類の決まった平均的な条件の固定数値を基に、
度数データを設計製造。 |
|
 設計年度の詳しい説明はコチラ 設計年度の詳しい説明はコチラ |
現在、販売されている遠近両用レンズは、開発から10年以上前のモノから、
最新設計まで多様です。 最新設計レンズの開発!
→遠近両用レンズの弱点を補う為、視野の広さ・ユレ・歪みの低減を目的にされています。
|
 |
『うーん・・むずかしいな〜。有名ブランドのレンズを選べば大丈夫?』 |
『有名ブランドの遠近といっても一社で4タイプにも分類されます。』
『加入度が高くなる方や見え方にこだわる方は上級製品をオススメします。』
『今回は加入度1.00Dですので、見え方にそれ程大きな違いが出ません。』
『どうしましょうか?』 |
 |
 |
『初めてだし・・。余り高いのも・・・。でも安いのも・・・。どうしよう?』 |
『設計の違いは、テストレンズで体験できます。』
『比較して頂き、予算と相談しましょう!!』 |
 |
|
| HOYA・Nikon・SEIKO・東海など、各メーカーの遠近両用もグレード(累進設計・製造工程・開発年度別)に分かれ、更に累進帯長別に分類されます。 |
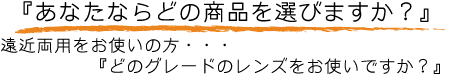 |
| 遠近両用累進レンズのグレード一覧はコチラ |
|